【開催報告】データサイエンス学部 第1回シンポジウム「WiDS TOKYO @ Otsuma Women’s University~Next Generationへの招待状」
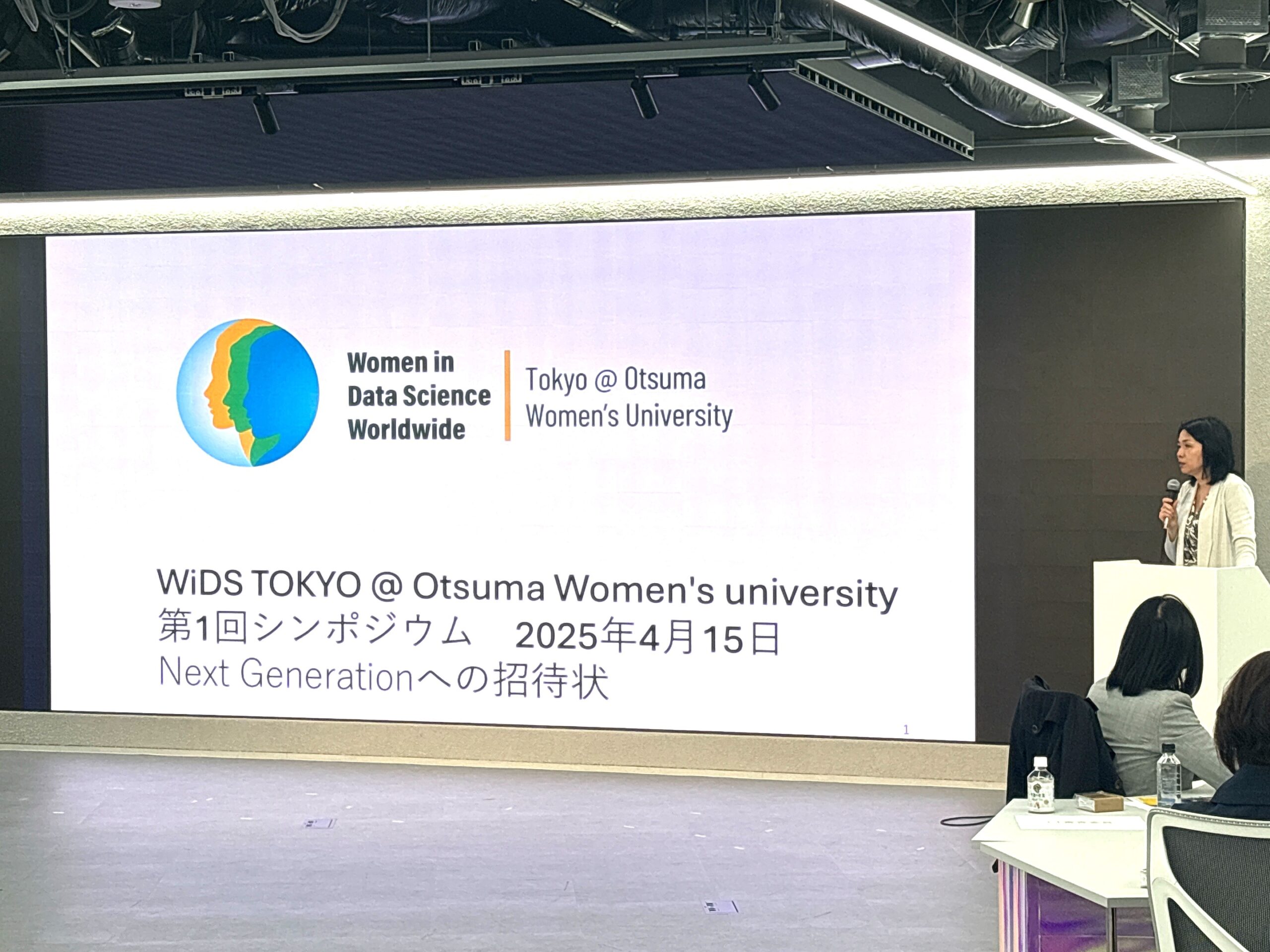)
大妻女子大学は、データサイエンス・AIの現在を見つめ、将来を語り、若い世代をこの領域にいざなうことを目的とした第1回シンポジウム「WiDS TOKYO @ Otsuma Women’s University~Next Generationへの招待状(主催:学校法人大妻学院、会場:ウイングアーク1st株式会社 D.E.BASE)」を4月15日(火)に開催し、企業・高等学校・官公庁・一般の方(ZOOM視聴)など幅広い方々の参加がありました。
本学では2025年4月の「データサイエンス学部データサイエンス学科」開設にあたり、今後の「生成AI時代」において、次の時代を担う若い世代をデータサイエンス・AI領域へ多数いざなうことが極めて重要であるとの認識から、「WiDS TOKYO @ Otsuma Women’s Universityプロジェクト」を展開。同プロジェクトは、スタンフォード大学の ICME(Institute for Computational & Mathematical Engineering)が創始したWiDS(Women in Data Science)プロジェクトと連携して行われるもの。WiDSプロジェクトは性別に関係なくデータサイエンス分野で活躍する人材の育成を目的としたもので、現在はスタンフォード大学から独立した団体が運営し、世界各地でシンポジウム等の活動を行っており、その一環として本シンポジウムを開催しました。
本シンポジウムは同学部・小野陽子教授による「WiDS TOKYO @ Otsuma Women’s University が目指すもの」をテーマとした基調講演でスタートしました。
続いて、「生成AI時代のデータサイエンス教育~Next Generationの育成にむけて~」をテーマに、酒井知果氏(華頂女子高等学校)、ドゥラゴ英理花氏(聖徳学園中学・高等学校)、平野恵氏(大妻中野高等学校)によるパネルディスカッションが行われ、各学校におけるデータサイエンス教育の紹介のほか、「データサイエンス教育に生徒たちを巻き込む秘訣」では、「データサイエンスと探究は親和性が高く、課題設定と生徒の興味・関心を合わせることが必要」と教育方針なども示され、今後のデータサイエンス教育について有意義な議論がなされました。
後半では、「第1回ライトニングトーク・コンペティション」の結果発表・授賞式が執り行われ、「データサイエンス × SDGs × 任意のキーワード」をテーマに、アイデアや今後の抱負が全国から52件寄せられ、最優秀賞1件、優秀賞2件が発表され、協賛企業から副賞が贈られました。
※各受賞者の所属は2024年12月~2025年1月の応募時点での所属となります。
※協賛企業からの副賞は「Wolfram Research, Inc.:Wolfram Alpha Notebook Edition 1年分のサブスクリプション」、「株式会社オライリー・ジャパン:書籍『ゼロからはじめるデータサイエンス第2版』、オリジナルトートバッグ」、「全日空商事株式会社:ANAオリジナルグッズ各種」
結果および審査委員のコメントは以下のとおり。
■最優秀賞
〇大妻中野高等学校 久次珠代さん、西巻悠さん、松本朋佳さん
タイトル:「ジェンダーバイアスを解消する」
▼審査委員からのコメント
・啓発対象として5・6歳の園児に注目したのは、大変ユニークで良いですね!企業を対象とした方策も、AIに100%頼るのではなく、人間の判断を入れるというのは、今後のAI社会において重要な点だと思います。
・日本社会が長年抱え、対応が進んでこなかった「難題」に対して、果敢に挑戦したプレゼンテーションだと感じました。特にアプローチが重要な対象を、管理職層と幼児層に絞り込み、それぞれの対策を検討した点は説得力がありました。中でも、幼児層への対応として、「ランドセルの色」や「なりたい職業」に対するバイアスを生じさせないことを目指す取り組みは実践的で、ぜひ試してほしいと思える内容でした。
■優秀賞
〇聖徳学園高等学校 村上愛幸さん
タイトル:「ケニアのジェンダー問題」
▼審査委員からのコメント
・女性の地位向上と森林伐採の削減を掛け合わせて解決しようという着目点、実際に解決につなげるにはより多くのデータ収集とさまざまな視点からの検討が必要だと冷静に分析していることが素晴らしいです。期待しています!
・全体を通じて、データをもとに論を展開することに工夫をこらしたプレゼンテーションだと思いました。動画の見せ方も分かりやすかったです。ケニアの男女格差の深刻さ、解決策としてのソーラークッカーの使用状況や効果など、データがあったことで理解が深まる内容でした。森林モラトリアムの取り組みについては、インドネシアの事例に加え、ケニアでの導入法についても提案があるとより説得力が増したと思います。
〇大妻中野高等学校 長坂未央さん、都甲理音さん、野元百合奈さん
タイトル:「住み続けられる街をつくるために観光と経済と向き合う」
▼審査委員からのコメント
・アプリの名前やどうやってポイントが貯まるかも検討していて、すぐに実現できそうですね!より多くの人にこのツアーに参加してもらうために、楽しさやメリットを明確にしてPRしていく方策をぜひ考えてみて下さい。
・地域が抱えるオーバーツーリズムについて、現状の分析から解決法の検討、実施後の展開まで、すべての段階でデータを活用する視点が盛り込まれていた点、解決法の実現可能性の高さ、さらに脱炭素社会の構築まで目配りされていることも含め、よく練られたプレゼンテーションだと思いました。グラフの使い方も分かりやすかったです。ぜひこのプロジェクトを具体化させてほしいと思います。
▼全体に対する審査委員からのコメント
・社会にあまり気づかれていない問題に着目したり、若者らしい視点に富んだ解決策が考え出されていて、わくわくしながら審査させていただきました。皆さんがこれから成長し、さまざまな経験を積み、データを収集、分析、活用することによって、より具体的な解決策にバージョンアップされること、そしてこれからの女性をリードして、皆さん自身が解決に向けてどんどん行動されていくことを、同志として心から期待しています!
・アイデアもよかったですが、スライドも見やすく、音声も聞きやすく見ている相手を飽きさせない工夫があったプレゼンテーションでした。今後も、ぜひ想いの伝わる活動を期待したいと思いました。
・身近なテーマから国際的な課題まで問題設定が幅広く、発想の豊かさを感じました。それらの問題をいかに解決するかという点についても、データを活用して模索しようという熱意が伝わってきました。データを根拠とすることで、プレゼンテーションの説得力は飛躍的に増します。正しく問題を解決し、理解を得るには、さまざまなデータを活用することが欠かせません。これからも納得感を高め、議論を深めるプレゼンテーションを工夫していってほしいと思います。
※ライトニングトーク審査委員
小原愛氏(一般社団法人Japan Innovation Network イノベーション加速支援グループ ディレクター)
小木しのぶ氏(株式会社NTTデータ数理システム 営業部部長)
永山悦子氏(毎日新聞社 論説室 論説副委員長)
平川祥子氏(国立研究開発法人 科学技術振興機構)
小野陽子(大妻女子大学 データサイエンス学部 教授)
また、今回の結果について、審査委員の平川祥子氏(国立研究開発法人 科学技術振興機構)からは、「データサイエンスは、正しい情報を見極める力、複雑な社会で解決策を作る共通言語。ぜひ興味関心を持って挑戦して欲しい」と未来のデータサイエンス人材にエールが送られました。
続いて、2つの協賛団体のセッションがあり、「NEC」からは、大橋真琴氏(アナリティクスコンサルティング統括部:写真左)がZ世代ながらデータサイエンティストとして働いている現状や業務範囲について紹介するほか、さまざまな業界の数値を扱い課題解決の提案を行う楽しさを説明されました。本シンポジウムの会場としてお貸しいただいた「ウイングアーク1st株式会社」からは、鹿島忍氏(サステナビリティ推進室:写真右)が中高生を対象とした「The Mirai Empowerment Program」を紹介。2023年よりSDGsテーマの教育を目的とした修学旅行の受け入れ先として、中高生にSDGsに関する学習の場を提供し、2025年2月末時点で全国約300人の生徒が参加している実績があります。5月から本プログラムの無償提供が開始されますので、詳細は「中高生を対象とした「The Mirai Empowerment Program」を始動」をご覧ください。
最後に、今川新悟氏(文部科学省 高等教育局 専門教育課 専門官)から講評があり、「今回発表いただいた3校のような先進的な取り組みを経験した生徒や情報Iを学んだ生徒が大学にも入学してきているので、高等教育におけるデータサイエンス分野をさらに発展させていかなければいけないと感じている。今回のコンペティションのテーマでもあったSDGsという答えのない課題に取り組む際に、データサイエンスの知識を活用することは必須であり、課題の設定の仕方やデータの取り方、活用の仕方が重要になってくると感じた。また、これだけ情報があふれている中で、データサイエンスの知識をもって、自分自身で正しいデータを精査しながら活用していくことも大切であると感じている。文部科学省としても、大学が企業や高校と連携しながらデータサイエンスを活用できる人材を育成することがとても重要だと考えている」と会が締めくくられました。
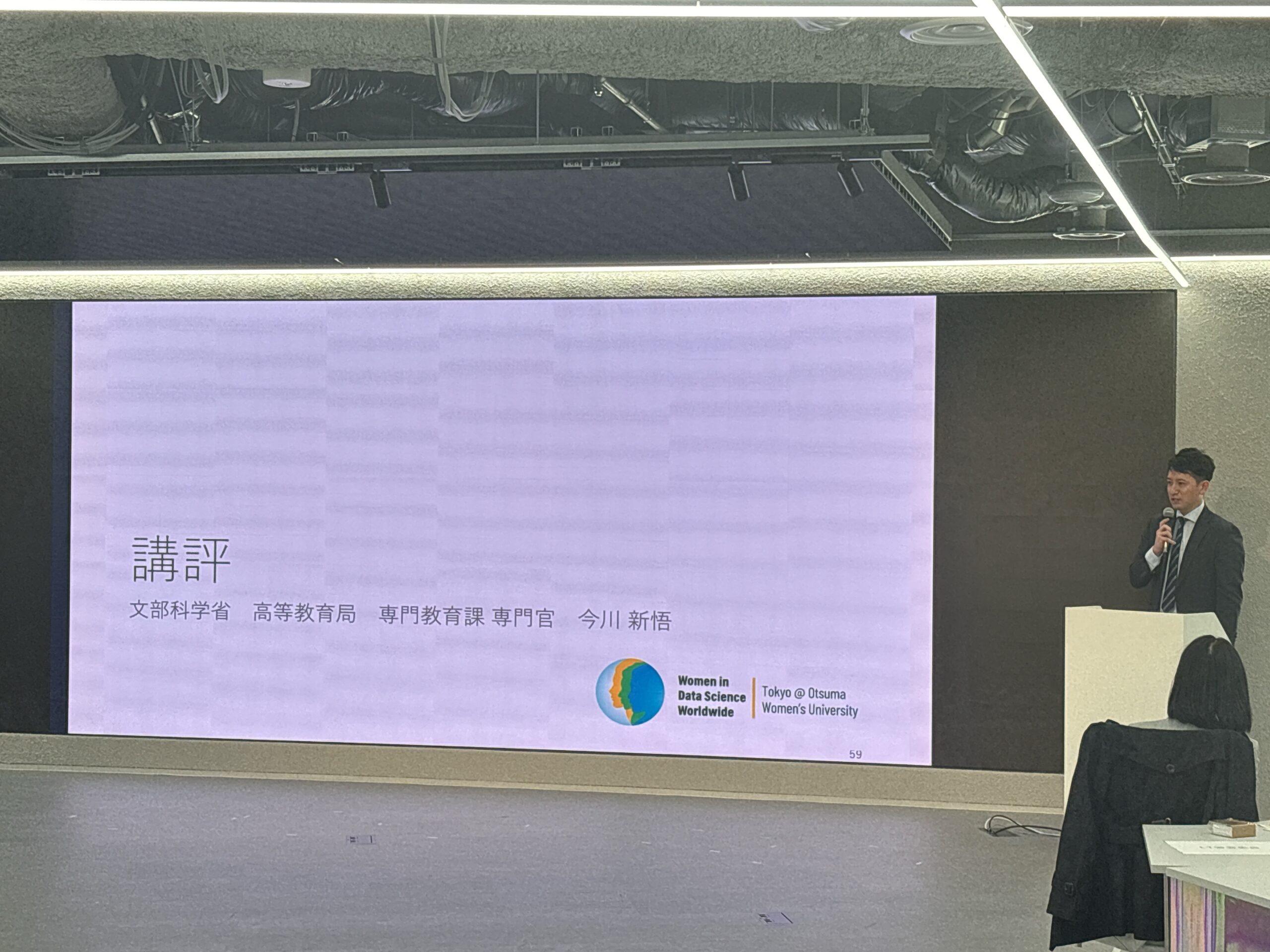)
なお、4月22日(火)に大妻女子大学のデータサイエンス学部特別講義として「数学×生成AIで未来の学びをデザインしよう」を千代田キャンパスで開催します。在学生や受験生だけでなく、中学・高等学校関係の方や一般の方も聴講可能(先着順・定員あり)となっておりますので、興味のある方は「一般聴講可能「数学×生成AIで未来の学びをデザインしよう」・データサイエンス学部特別講義 4月22日」をご覧の上、お申込みください。
WiDS TOKYO @ Otsuma Women's University
主催:学校法人 大妻学院
協賛:日本電気株式会社 / ウイングアーク1st株式会社 / Wolfram
Research, Inc./ 株式会社オライリー・ジャパン/ 全日空商事株式会社
後援:(一社)日本経済団体連合会
関連トピックス
最新トピックス
