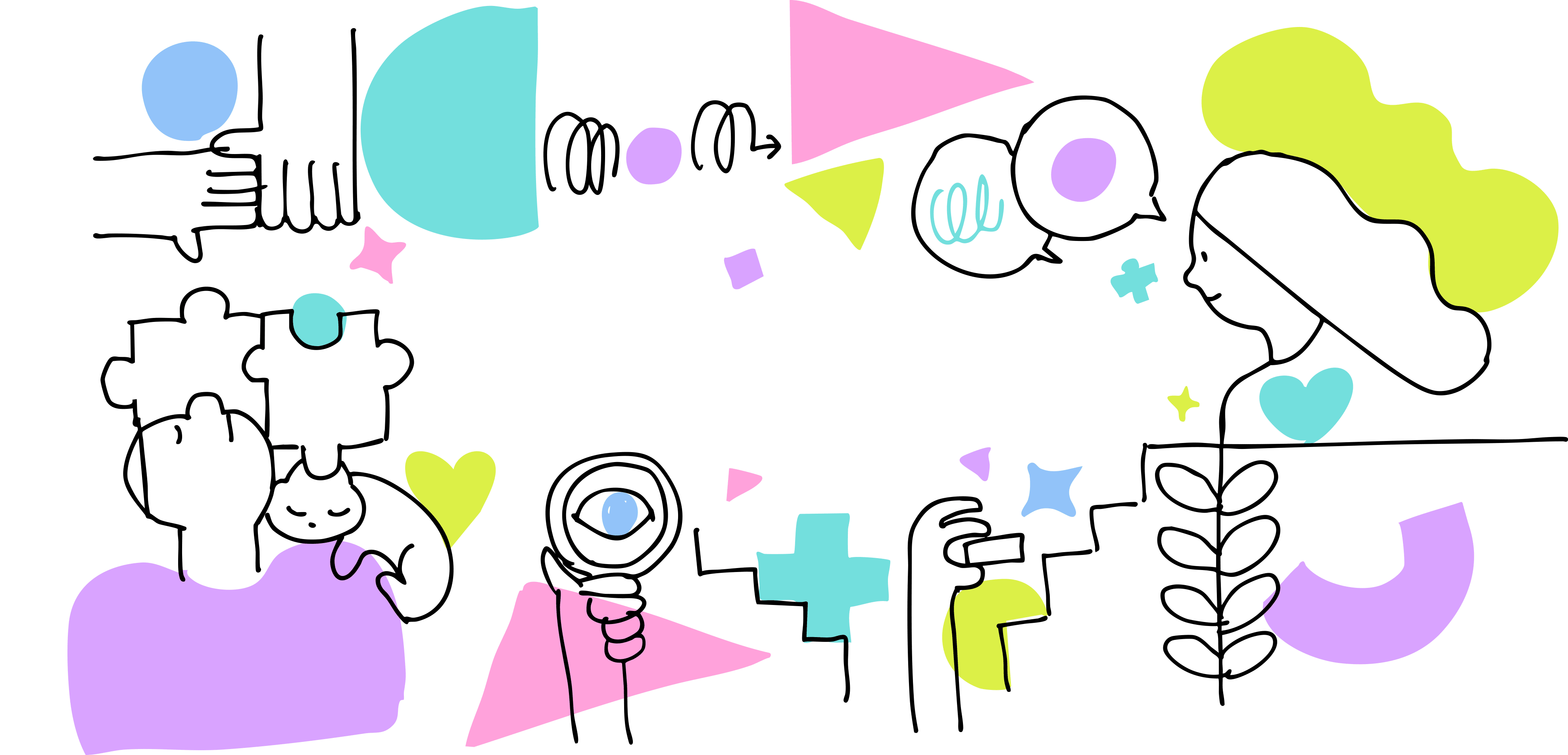
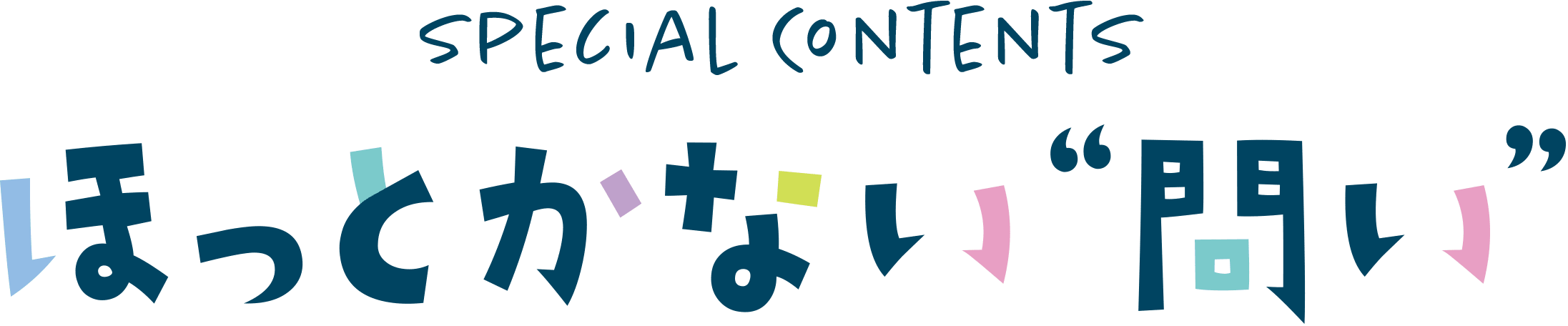

日常の中でふと感じた事や社会で起きている諸問題。
自分の中で芽生えた「気づき」に対して、ほっとかず、
どう捉えて向き合うかで
世の中はもっと良くなるかもしれません。
そんな「ほっとかない問い」について
4学科の教員が専門分野の視点で回答しています。
同じ問いに対する分野別の考え方・解決方法の違いを
あなたはどう思いますか?
共感・納得・疑問・反論・驚きなど、
さまざまな感想や反応を持つことで
新しい価値観に出会えるかもしれません。
自分の中で芽生えた「気づき」に対して、ほっとかず、
どう捉えて向き合うかで
世の中はもっと良くなるかもしれません。
そんな「ほっとかない問い」について
4学科の教員が専門分野の視点で回答しています。
同じ問いに対する分野別の考え方・解決方法の違いを
あなたはどう思いますか?
共感・納得・疑問・反論・驚きなど、
さまざまな感想や反応を持つことで
新しい価値観に出会えるかもしれません。
Question. 01
#意見の違いをほっとかない
意見の合わないクラスメイトがいます。
先生は仲良くしろっていうんですけど、
仲良くしなくちゃダメですか?
Question. 02
#ふとした疑問をほっとかない
普通(当たり前)って何ですか?
Question. 03
#快適な環境づくりをほっとかない
子ども、高齢者、障害のある人、外国人、
誰にとっても心地よい居場所を作りたいです。
どんな工夫をしたら良いですか?
Question. 04
#社会の問題をほっとかない
闇バイトが横行しています。
社会のどこにどんな原因が
あると思いますか?
Question. 05
#女性の活躍推進をほっとかない
女性活躍ってなぜ必要なんですか?
女性活躍って
なぜ必要なんですか?
活躍を強制されているような気もしているのですが
どう思いますか。
Question. 06
#SNSトラブルをほっとかない
SNSにおける誹謗中傷は、
なぜ起こるのでしょうか?
Department
-
社会学科
- 身近な事柄を手掛かりに、
社会のあり方を広く深く学ぶ - フィールドワークや文献を通して、私たちを取り巻くさまざまな事象にアプローチしていく幅の広い学問です。ファッションや恋愛、アニメなどの若者文化から、家族、地域社会、国際関係といった多彩なテーマまで、社会学的に考察します。
- 身近な事柄を手掛かりに、
-
心理学科
- 人と人とのよりよい関係を目指して
「こころ」の問題に取り組む - 社会心理学と臨床心理学を中心にバランスよく心理学を学ぶことを通して、「人間の感情や行動を客観的かつ科学的に捉えていく分析力」、「さまざまな人々や社会の中で共存するための傾聴力と自己表現力」、「自己と他者を理解し主体的に他者と協働する人間関係力」を身につけます。
- 人と人とのよりよい関係を目指して
-
福祉学科
- 福祉マインドを多様な分野で生かす
プロフェッショナルになる - 生活上のさまざまな課題を抱える人を理解し、誰もが暮らしやすい社会の実現に向けて、専門的な支援や制度の活用、社会資源の開発を目指します。実践的な授業や海外フィールドワークを通して、人々の生活や地域社会を読み解く視点、思考を学びます。専門職としてだけではなく、ビジネス分野でも活躍できる人材を育成します。
- 福祉マインドを多様な分野で生かす
-
共生デザイン
学科- 多様性とグローバルな視点を養い、
さまざまな角度から共生のあり方を学ぶ - 共生社会を実現するために、人間の多様性に関する知識、グローバルな視点、実践的なコミュニケーション力を基礎とし、社会学・心理学・福祉学を融合させながら学びを進めます。また、フィールドワークを通じて、国内外の地域社会や職場の課題に取り組み、さまざまな角度から共生のあり方を考え、多様な人々と共に働くことができる人材を育成します。
- 多様性とグローバルな視点を養い、
